<音楽産業のおよび音楽文化の衰退について>
早稲田大学社会科学部 政策科学研究
諏訪 靖典
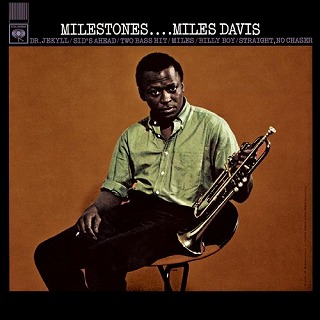
研究動機
音楽は私たちにとってとても身近な娯楽であり、歴史の長いものであると思う。その音楽について、近年、音楽産業の衰退が叫ばれるようになり、そのような記事を目にする機会が多い。インターネットの音楽配信サービスの発達や携帯電話を用いた手軽なダウンロードの普及、また、音楽の趣味の多様化が進み、これまで以上にCDの売り上げは下がっていくだろうということが予測できる。また、売り上げにとどまらず、他にも多くの問題がある。このままではは日本の文化の衰退につながってしまうのではないか、この先日本の音楽産業・音楽文化は大丈夫なのだろうかという思いに駆られ、このテーマを選んだ。これから先、どのような手段を講じれば音楽産業および音楽文化が活性化するのかを研究したいと思う。
章立て
- 第一章 音楽に関連する諸問題
- 第二章 海外との比較
- 第三章 これから講じられるべき対策
第一章 音楽に関する諸問題
 出展:日本レコード協会
出展:日本レコード協会
売り上げの問題。上のグラフは最近10年間のCDの年間の総生産数をグラフにしたものだが、見るとわかる様に、10年前と比べると、2008年の年間のCDの総生産数はおよそ半分になっていることがわかる。それに比べ、携帯電話やパソコンを利用した音楽のダウンロードサービスの利用者は増加しているが、これは単価が安いので、あまり売り上げには貢献できないのではないかと思う。また、違法な音楽の無料ダウンロードによって打撃を受けているという面もあると思われる。
著作権の問題。音楽著作権の管理をしている団体として、社団法人のJASRACが有名だが、この団体が著作権を独占しているという問題がある。この団体が著作権を独占していたことによって、後発業者の参入が阻害されているというのがこの問題の焦点とされており、今年の2月に公正取引委員会が排除措置命令を出した。これによって新規参入の問題は幾分か改善されるように思いますが、新規業者が参入した後も問題が現れてくるのではないかと思う。(http://jp.ibtimes.com/article/biznews/090228/30363.html)
事業仕分けの問題。事業仕分けによって、文化予算が大幅に縮小されることになったがここにも問題があるようだ。オーケストラの助成金が大幅に削減されると、助成金で運営が行われている全国のオーケストラは壊滅状態となるようである。(定期公演会のプロジェクトの廃止、オーケストラが行う子供のための音楽教室の廃止など。)さらに、この予算の削減はオーケストラに限らず、オペラや能楽、狂言、落語などの伝統芸能にも影響を与えるということが問題となっている。http://www.asahi.com/culture/update/1207/TKY200912070349.html)
第二章 海外との比較
イギリスの文化政策の特徴
イギリスの芸術活動は王侯貴族の庇護と豊かな市民層による自立的で自主的な支援という2面性をもった歴史がある。
それは現在でも残っており、文化行政において芸術の自由と独立を保つための「アームズ・レングスの原則」と呼ばれる芸術が行政と一定の距離を保ち、援助を受けながらしかも表現の自由と独立性を維持する施策をとっている。
文化を所管する国の機関は、文化・メディア・スポーツ省(DCMS)であり、文化の活動を通じてすべての国民に生活内容の質の向上の機会を与えることを目的としている。そのため、同省の任務は、不必要な規制や発展を拒む障害物を排除し、効率の良い競争市場を育み、国の内外で高く評価される文化、メディアの振興に努めることにあるとされている。
国は美術館、劇団、交響楽団等に巨額な支援を行っているものの、DCMSが行うのではなく、アーツカウンシルという専門家集団による公的機関を通じて助成が実施されている。また、国立の博物館、美術館の費用も約50%が国の助成で賄われ、残りは自力で資金調達が行われている。
<文部科学省HPから引用。>
アーツカウンシルとは…文化庁(DCMS)から助成を受けている専門家集団(この中には実際で活動しているアーティストも含まれる)。受けた助成は各地域に配分する。民間芸術団体、芸術家に対して助成を行う。政府から距離を置いている。芸術団体の発展,芸術鑑賞の機会の増進,政府,地方機関などへの助言,協力などを行っています。各地域にアーツカウンシルが存在する。
日本…文化庁のみ
イギリス…文化庁、アーツカウンシル。
<なぜ芸術文化を保護する必要があるのか?>
何故芸術文化を保護する必要があるのか。それは長期的に見た場合、芸術文化が育たなければ観光機会が損なわれてしまうためである。
例えば日本の場合を考えると、アニメや漫画、歌舞伎、などが盛んな文化としてとりあげられると思う。それらは現在、重要な観光資源になっていると思う。しかしこれらの分野には、前者ならば技術および技術者の流出や、後者には先に述べた事業仕分けによる予算の削減などの問題がある。このままの状態が続いていけば、数十年後にそれらの文化が廃れてしまう可能性もありうるのではないかと考えた。
第三章 これから講じられるべき対策
なぜ事業仕分け問題が起こったのか。
なぜ、事業仕分けに際して各団体から大きな反発があったのだろうか。それはおそらく仕分けを行った側がその事業の必要な部分、不必要な部分をごちゃ混ぜにして仕分けを行ってしまったからだろう。また、1事業につき一時間しか議論の時間が用意されていなかったことも問題になるだろう。以上の点を考慮すると、イギリスの様なアーツカウンシルを日本にも導入するべきなのではないかと考える。
アーツカウンシルを導入すると
専門家が助成するか否かを判断するので、より無駄のない援助を行うことができる。
再び仕分けが行われた場合でも、団体と専門家で議論をおこなうことができる。
地方にもカウンシルを設置できれば、地方で活動する芸術家が活動を行いやすくなる。
地方に住む一般市民が芸術文化に接する機会が増える。
などの効果が考えられる。
関連ホームページ
社団法人日本レコード協会(http://www.riaj.or.jp/index.html)
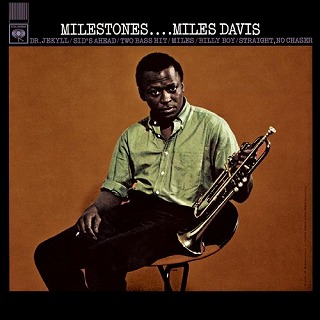
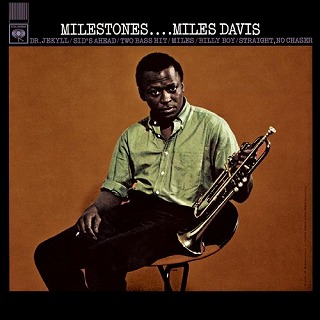
 出展:日本レコード協会
出展:日本レコード協会