巹偑偙偺僥乕儅偵偮偄偰尋媶傪偟傛偆偲巚偭偨偺偼丄憗堫揷戝妛僆乕僾儞壢栚偱庴偗偨亀web價僕僱僗亁偲偄偆庼嬈偐傜丄web價僕僱僗偵娭偡傞嫽枴偑峀偑偭偨偙偲偑偒偭偐偗偱偁傞丅
偦偺拞偱丄摿偵嫽枴偑傂偐傟偨偺偑亀僋儘僗儊僨傿傾亁偲偄偆庤朄偱丄巹偨偪偵偲偭偰嵟傕恎嬤偵巊傢傟偰偄傞庤朄偱偁傞傛偆偵巚偆丅巹偑弶傔偵抦偭偨僋儘僗儊僨傿傾偺幚巤椺偼丄QR僐乕僪偱偁偭偨偺偩偑丄嬃偒偲偲傕偵丄偄傑偺忣曬幮夛偵尒崌偭偨庤朄偩側偲姶偠偨丅
尰嵼丄忣曬壔幮夛偑敪揥偟懕偗偰偄傞拞偱丄偝傑偞傑側僨僶僀僗偑悽偺拞偵尰傟丄懡偔偺恖乆偑僱僢僩傪棙梡偡傞帪娫傗婡夛偑憹偊偮偮偁傞丅嵟嬤偱偼僗儅乕僩僼僅儞偺晛媦偑婰壇偵怴偟偄偩傠偆丅
崱屻傕怴偟偄僨僶僀僗偑悽偺拞偵弌偝傟懕偗傞偲巚傢傟傞偑丄僋儘僗儊僨傿傾偺宍偼偙傟偐傜偳偆曄梕偟偰偄偔偺偩傠偆偐丅尰嵼傑偱偺幚巤椺傪尒側偑傜丄崱屻偺僋儘僗儊僨傿傾偵懳偡傞壜擻惈偵偮偄偰尋媶偟偰偄偒偨偄偲巚偆丅
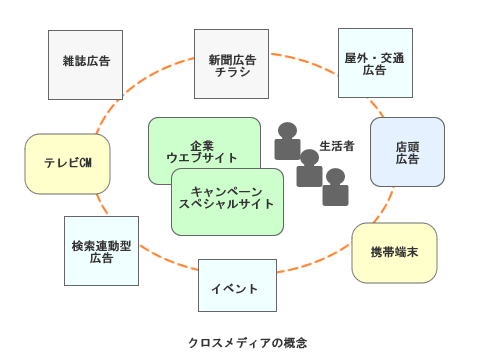
乽僋儘僗儊僨傿傾乿偲偼丄堦偮偺忣曬傪巻攠懱丄僀儞僞乕僱僢僩丄儌僶僀儖丄DVD側偳偝傑偞傑側昞尰攠懱傪慻傒崌傢偣偰丄徚旓幰傊岠壥揑偵揱偊傞偙偲丅偦傟偧傟偺儊僨傿傾偑帩偮挿強偲抁強傪曗偄側偑傜忣曬揱払偵憡忔岠壥傪帩偨偣傞偺偑摿挜偱丄儅乕働僥傿儞僌愴棯偱偼桳岠側昞尰曽朄偲偟偰昡壙偝傟偰偄傞丅
僥儗價CM偺乽懕偒偼僂僃僽偱乿傗丄億僗僞乕側偳偺巻攠懱偵QR僐乕僪傪婰嵹偟偰僀儞僞乕僱僢僩傊偺傾僋僙僗傪桿摫偡傞庤朄偑揟宆椺偱偁傞丅
偪側傒偵丄條乆側宍懺偺忣曬傪丄僨僕僞儖僨乕僞壔偡傞偙偲偵傛偭偰僐儞僺儏乕僞乕忋偱堦尦揑偵埖偊傞傛偆偵偟丄偦傟傜偺僨乕僞傪憡屳偵娭楢晅偗偰摑崌揑偵埖偆儅儖僠儊僨傿傾偲偼丄懡條側昞尰攠懱傪嬱巊偟偰堦憌岠壥揑側揱払傪峴偆偲偄偆揰偵偍偄偰丄嬫暿偝傟偰偄傞丅
偦偺偨傔丄偟偽偟偽乽儅儖僠儊僨傿傾偑壛嶼揑側傜丄僋儘僗儊僨傿傾偼忔嶼揑偱偁傞乿偲尵傢傟傞丅

塃恾偺乽儅僗4攠懱偐傜僀儞僞乕僱僢僩傑偱傪崌傢偣偨1擔偺儊僨傿傾愙怗憤帪娫乿偺僌儔僼偐傜尒偰傢偐傞傛偆偵丄PC丒実懷揹榖偺偲傕偵僱僢僩愙懕帪娫偑憹壛偟懕偗偰偄傞丅偦偺偨傔丄僥儗價傗巻丒峀崘攠懱偐傜偺僀儞僞乕僱僢僩傊偺傾僋僙僗偑丄傛傝堦憌桿摫偟傗偡偄忬嫷偵偁傞偲尵偊傞丅
尰嵼偱偼丄僗儅乕僩僼僅儞偑晛媦偟巒傔丄僀儞僞乕僱僢僩傗実懷揹榖偵尷傜偢偵偝傑偞傑側僨僶僀僗偑憹偊偰偄傞丅偦偺偨傔丄怴偨側僨僶僀僗偺慻傒崌傢偣偑惗傑傟丄怴偟偄僋儘僗儊僨傿傾偺宍傕抋惗偟偰偄偔偲巚傢傟傞丅
戞堦復偱傕椺偵偁偘偨偑丄峀崘傪攝怣偡傞応崌丄奨拞偱庤偵庢傝傗偡偄巻攠懱傪梡堄偟偰偍偒丄偦偺巻峀崘偵Web僒僀僩傊偺傾僪儗僗傗QR僐乕僪傪婰嵹偟偰偍偗偽丄嫽枴傪帩偭偨恖偑僀儞僞乕僱僢僩偐傜娙扨偵傾僋僙僗偱偒傞丅
偙偺傛偆偵丄巻攠懱偐傜僀儞僞乕僱僢僩傊宷偑傞僋儘僗儊僨傿傾峔憿傪嶌偭偰偍偔偙偲偱丄巻攠懱偩偗偱偼昞尰偟偒傟側偄懄帪惈傗忣曬偺峀偑傝傪傕偭偨忣曬偑揱払壜擻偲側傞丅
佱嶲峫暥專佲