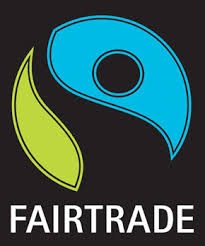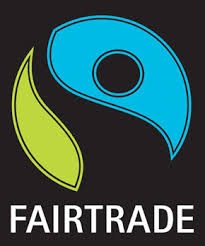フェアトレードの推進
政策科学研究ゼミナールⅠ
社会科学部2年
狐塚佑姫
研究動機
高校時代、聖書の授業で児童労働に関するDVDを見てから、児童労働に興味を持った。例えば、私たちが日々口にするチョコレートの原材料であるカカオ豆の8割はガーナ産で、ガーナでは14歳以下の子供のうち2人に1人が働いているという事実がある。当時の私は、同年代の子供が学校に行けず働いていることに心を痛めた。
児童労働の問題を改善するためには、様々な方法があり、その中の一つがフェアトレードだ。児童労働の改善と向き合うにあたり、フェアトレード貿易の推進は、私が日本にいながらも支援につなげることができるため、注目することに決めた。
章立て
- フェアトレードとは
- なぜフェアトレードが推進されてるのか
- 海外におけるフェアトレード事例
- フェアトレードタウンの事例
- 日本におけるフェアトレードタウンの事例
- フェアトレードの広がらない日本
- 現状の整理
- 今後の方針
- 参考文献
1.フェアトレードとは
フェアトレード(Fair Trade)=公平貿易
発展途上国で作られた作物や製品を適正な価格で継続的に取引することによって、生産者の持続的な生活向上を支える仕組み
出所:分かち合いプロジェクト「フェアトレードとは」
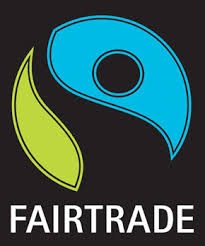
FLOの認証ラベル
出所:フェアトレード・ラベルジャパン

WFTOのマーク
出所:World Fair Trade Organization
2.なぜフェアトレードが推進されてるのか
ITA(国際熱帯農業研究所)が実施した西アフリカのカカオ生産における児童労働の調査では、コートジボワールだけで約13万人の子供が農園での労働に従事している。
カカオ農園は小規模な家族経営である場合が多く、子どもが家族の手伝いとして働いているケースもあるがコートジボワールではおよそ1万2000人の子供が農園経営者の親族ではないことが分かっている。
農園経営者の親族の子ども(6~17歳)であっても、その1/3は一度も学校に行ったことがない。
また、親族以外の子どもの中には「何らかの仲介機関」に他国から拉致され、強制的に働かされている子どももいる。
3.海外におけるフェアトレード事例(イギリス)
海外にはフェアトレードが盛んな国が多くある。その一例にイギリスがある。1970年ころのイギリスでは発展途上国からの工芸品を公正な価格で取引するという形で存在していたが、知名度は低かった。しかし、現在では80パーセントの人がフェアトレードを認知しており、そのうちの9割近くが質や安全面で信頼している。
1992年にフェアトレード・ファウンデーションが設立された。フェアトレード・ファウンデーションとは、「国際的に合意されたフェアトレード基準に従ってイギリスの製品に関するフェアトレードマークの使用の許可をする独立した非営利団体」のことである。日本では、イギリスのフェアトレード・ファウンデーションの日本支部にあたる組織の「フェアトレード・ジャパン」が認証を行っている。この組織は日本の公正取引委員会とは種類を異にする団体だ。
イギリスでフェアトレードが普及下理由は3つある。
- 1つ目は、教会の存在だ。
キリスト教信者が多いイギリスでは、毎週日曜日に礼拝があるため人が集まる機会が多く、一気に知名度が上がったと考えられる。
さらに、キリスト教のもつ、隣人愛の思想がフェアトレードの概念と一致することも、イギリスでの普及の要因と推測できる。
- 2つ目に、フェアトレード・スクールの存在だ。
フェアトレードを推進する学校を「フェアトレード・スクール」とし、これまでにイギリス内で1000校を超える学校が認定されている。
フェアトレード・スクールに認定されるためには、いくつかの基準がある。
- まず「フェア・アウェア(意識)」校内のフェアトレードについての知識や意識を調査し、フェアトレードに関する授業を実施。
- 次に「フェア・アクティブ(行動)」校内でフェアトレード組織を作りアクションプランを策定、イベントやキャンペーン、講演、フェアトレードに関わる社会見学などの具体的な活動を実施。
- 最後に「フェア・アチーバー(達成)」では、校内のフェアトレードポリシーの策定、フェアトレード商品の利用、フェアトレードに関する授業を恒常的に行うこと
などが求められる。これらをすべてクリアした学校が、フェアトレード・スクールとして認定される。
- 3つ目は、フェアトレードタウンの成功だ。
フェアトレードタウンとは、「国際フェアトレード認証ラベル製品を積極的に購入するなど、フェアトレードをサポートする努力を表彰され、その称号を得た、町、地域」のことだ。
2000年にランカシャーという街がフェアトレードタウンを宣言して以来、500以上設立され、現在23カ国に1000以上存在する。「暮らしの中にフェアトレードが溶け込む」ことをコンセプトにしており、ロンドンオリンピックでは認証コーヒー1000万杯と認証バナナ700万本の売り上げ実績を持つ。フェアトレードタウンの役割には認証ラベル製品がすぐに手に入る環境整備や普及イベントの企画、実行など達成すべき項目がある。
4.フェアトレードタウンの基準
- 基準1:推進組織の設立と支持層の拡大:様々な分野の人からの支持
- 基準2:運動の展開と市民の啓発:積極的なメディア進出
- 基準3:地域社会への浸透:元の企業や団体(学校や市民組織)がフェアトレードに賛同
- 基準4:地域活性化への貢献:地産地消やまちづくりなどコミュニティ活動と連携
- 基準5:地域の店(商業施設)によるフェアトレード産品の幅広い提供
- 基準6:自治体によるフェアトレードの支持と普及
国際フェアトレード基準の概要
| 経済的基準 |
社会的基準 |
環境的基準 |
フェアトレード最低価格の補償
フェアトレード・プレミアムの支払い
長期的な安定した取引
前払い
| 安全な労働環境
民主的な運営
労働者の人権
地域の社会発展プロジェクト
児童労働・強制t労働の禁止
| 農薬・薬品の使用に関する規定
土壌・水源の管理
環境にやさしい農業
数奇栽培の奨励
遺伝子組み換え(GMO)の禁止
|
5.日本におけるフェアトレードタウンの事例
- 1.熊本
- 熊本市は、アジアで初、世界で1000番目のフェアトレードタウンとして認定されている。フェアトレードに関する講習会や勉強会、バザー出展、ファッションショーの開催等の実績があり、2014年3月28?30日に「熊本から世界へ ひとつなぐフェアトレード~第8回フェアトレードタウン国際会議in熊本~」も開催されている。しかし、熊本市のフェアトレードタウンを紹介するブログは2015年9月以降更新がなく、一時的なブームで終わっているのではないかと推測できる。
また、フェアトレード認知度の全国平均は25パーセントであるのに対し、熊本市の認知度は32パーセントだ。全国平均を上回っているものの、決して高い数字ではない。
- 2.名古屋
- 名古屋市はでは2016年5月7日「フェアトレードコーヒー・サミット」、「秋のフェアトレードタウンまつりin Nagoya TV TOWER」を開催するなど活発な普及活動がされている。さらに、毎年5月の第2土曜日を「世界フェアトレードデーなごや」と設定している。名古屋がここまでフェアトレードに関するイベントが活発である理由として、名古屋市の河村市長が積極的に企画、参加していることが関連していると言える。市長がフェアトレードタウンを推進することは、フェアトレードタウンに必要とされる大事な基準の1つである。
6.フェアトレードの広がらない日本
日本でフェアトレードが普及しない理由は大きく3つに分けられると考えられる。
- フェアトレード製品は一般のものと比べて値段が高価であることだ。雇用を生み、正当な賃金を払うことを目的とし、フェアトレード認証費用もかかるため、輸出価格がたかくなってしまう。
- フェアトレード製品は、一般のアジア雑貨と比べて品質が劣ることが少なくないということだ。現地の技術指導体制が整っておらず、品質管理が未熟なことがある。また、日本で販売されているアジア雑貨は日本人がプロデュースしていることも少なくないため、比べるとどうしても品質の面で劣ってしまうのだ。
- フェアトレードタウンが企業のブランドイメージに利用されているということだ。大企業はフェアトレード製品を少量でも利用することでフェアトレード製品を使用していることをアピールする。つまり、フェアトレードのもたらすべき発展途上国への 効果を無視した利用がなされているのだ。
7.現状の整理
- 1.ブランド化
- 現在、フェアトレード・ジャパンがフェアトレード商品の認証活動をおこなているにもかかわらず、基本的には、誰でもどの企業でもフェアトレード商品を名乗ることが できる。これを逆手にとって、日本でもフェアトレード商品をブランド化し、フェアトレード商品を名乗ることが企業にとってのアドバンテージとなるような位置付けにして いきたい。
- 2.フェアトレード・スクールの開講
- 日本では、フェアトレード教育が全くと言っていいほど普及していないことが、フェアトレードの認知度が低い原因の一つだと考えられる。なぜ、フェアトレード商品を 買わなければならないのか、さらにはフェアトレード商品を購入することによって、どの地域のどんな境遇の人々の生活改善につながるのか、その過程を教育することは、日 本の道徳教育の一環にすることができないかと考えている。
8.今後の方針
2020年の東京オリンピックを見据えて、東京オリンピックでフェアトレードを普及させることを目標とし、東京オリンピックでフェアトレードを 推進しなければならない理由と、日本でフェアトレードが普及することによって得られるメリットを探していきたい。
また、フェアトレードといえばコーヒーやチョコレートといった倫理的認証の長い食品が真っ先に思いつくが、これは途上国からの産品がそういった ものに限定されていることに起因していることを理解し、より貿易額の大きい他の市場、例えば高機能な工業製品ではどうなのか追求していく必要がある。
9.参考文献
- フランツ・ヴェンデルホフ(2016).『貧しい人のマニュフェスト-フェアトレードの思想-』.東京.創成社.
- コナー・ウッドマン(2013).『フェアトレードのおかしな真実 私は本当に良いビジネスを探す旅に出た』.東京.英治出版.
- わかちあいプロジェクト「フェアトレードとは」
http://www.wakachiai.com/fairtrade/about_fairtrade/(最終アクセス2017/02/06)
- フェアトレードジャパン「参加団体インタビュー」
http://www.fairtrade-jp.org/interview/interview.html?id=1373(最終アクセス2017/02/06)
- フェアトレードジャパン「フェアトレードタウン」
http://www.fairtrade-jp.org/get_involved/000029.html(最終アクセス2017/02/06)
- みんなの地球村「フェアトレードタウン活動の紹介(熊本)vol.1」
http://info.felissimo.co.jp/kraso/act/earth/2014/08/vol1-1.html(最終アクセス2017/02/06)
- フェアトレードマルシェ「トップページ」
http://fairtrade-nagoya.com(最終アクセス2017/02/06)
Last Update:2017/02/25
©2017 Yuki Kitsunezuka.All rights reserved.