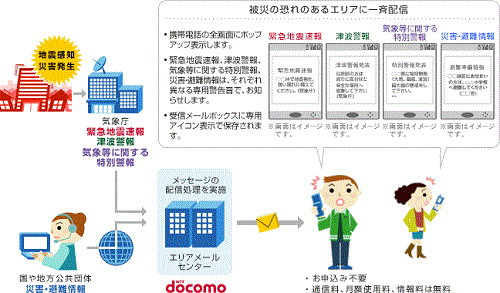
出典 docomoホームページ(https://www.nttdocomo.co.jp/service/areamail/)
マスメディアの特徴(ポジティブ面)
・大量発行による情報発信
・情報収集に基づいて発行されるため正確性が高い
マスメディアの特徴(ネガティブ面)
・一方通行による情報の発信
・情報発信までの所要時間が長い
ソーシャルメディアの特徴(ポジティブ面)
・情報を迅速に伝えることができる(リアルタイム性)
・お互いに情報を共有することができる(インタラクティブ性)
・拡散されるまでの所要時間が短い
ソーシャルメディアの特徴(ネガティブ面)
・誰でもどこでも情報発信できるため情報の正確さに問題あり
・デマなどによる誤った情報によって左右されることがある
以上のように、マスメディアとソーシャルメディアには、良い点・悪い点が存在する。実際に、東日本大震災や熊本震災を見てみると、お互いの良い部分と悪い部分が如実に表れていた。
互いの良い部分と悪い部分を相互補完することで災害に対する二次災害を減らすネットワークを作り上げることができるのではないか。
・インフルエンサーの存在
インフルエンサーとは、influence(影響を与える)からとられているもので、主に、著名人や公式アカウントといった、フォローの数と比較してフォロワーの数が圧倒的に多いアカウントを指す。
東日本大震災の時には、堀江貴文氏や津田大介氏というような著名人が、安否確認などの情報をフォロワーから集めて再発信することで、多くの人に情報を拡散することができた。
・Googleのパーソンファインダー
大手情報検索エンジンサイトGoogleが、パナマ沖震災の時に開発したサイト。人物を特定することができる情報を入力することで災害時にその人の安否を確認することができる。
世界に数多くのユーザーを持ち、世界各国の言語に翻訳されているGoogleはアクセスもスムーズで東日本大震災の時も大いに役立った。
緊急地震速報
国土交通省気象庁が行うシステム。震度4以上の震災を感知したとき、パソコン・携帯電話に地震発生を伝えるメール
を自動的に送る。携帯電話ではau・docomo・ソフトバンクの大手三社が参加しており携帯電話を持つ人々には確実に情報発信することができる。
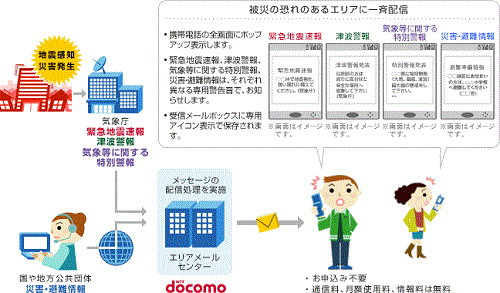
Ustとは、ニコニコ動画のようにストリーミング放送を行うことのできるシステム。ストリーミング放送というのは動画や音声を一部受信してその受信したものからどんどん流していくという放送方法のことで音声や動画をほぼ同時刻に流すことができるというメリットがある。
東日本大震災の時に、ある少年がテレビのNHK放送に映っていた津波の映像をそのままUstに流したことでほぼ同時刻に東北地方で起きていた津波や震災の映像を日本各地や世界各地に放送した。それを受けたNHKはその少年の行動を引き継ぎストリーミング放送を続けた。
これはソーシャルメディアのリアルタイム性とマスメディアの信頼度の高い情報を組み合わせた事例だと思われる。
・特務機関NERV
特務機関NERVとはもともとは新世紀エヴァンゲリオンに登場する機関。その機関名を使ったTwitterのアカウントがある。
そのアカウントは先ほども述べた緊急地震速報や気象庁の災害情報をそのままツイートすることでたくさんの人に情報を拡散することができる。2017年2月6日現在で約40万人のフォロワーが存在しており一度のツイートで40万人に情報を拡散することができる。
さらにTwitterにはリプライと呼ばれる返信機能も存在するため、この特務機関NERVはインタラクティブ性・リアルタイム性とマスメディア融合事例だと思われる。
・マスメディアとソーシャルメディアの融合事例をもっと探す。
・ソーシャルメディアが日本よりも普及している欧米に注目する
・熊本震災で活躍したDISAANA(ディサーナ)について調べる。
・ソーシャルメディアの弱点である情報の正確性を向上させる方法を考える.
Last Update:2017/02/28
© 2016 Miyamoto Naoki. All rights reserved.