
図1「いじめられる子ども」出典:Patch

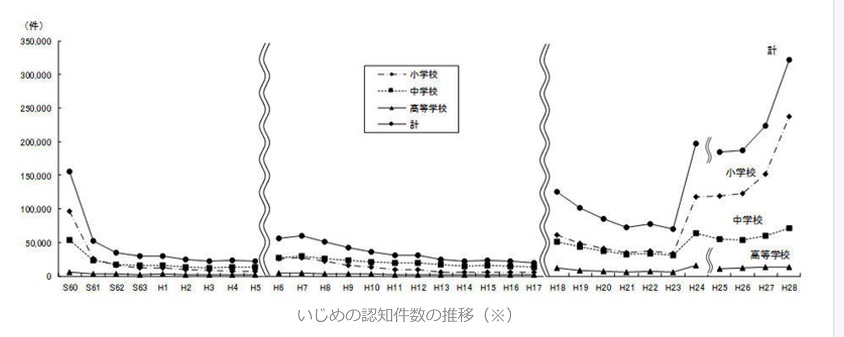
□香川県
香川県では子どもたちによっていじめをなくすためのサミットが開催されていた。2018年8月22日「いじめゼロこどもサミット」 2009年から自主的に集まった児童生徒による実行委員会が、県内の小・中学生に呼びかけて、3年に一度開催している。児童生徒一人ひとりがいじめを許さないという強い気持ちを持ち、自分たちの手でいじめをゼロにしようという意識を高めることを目的としたサミットである。 今回のサミットのテーマは、「『みんな』で感じ 考え つながろう」。いじめを一人で抱え込むことなく、友達と先生と、そして地域の人たちと「つながり」、「みんな」でいじめの問題について取り組んでいきたい、という実行委員80名の強い思いが込められたもの。香川県内の小・中学校の代表児童生徒約280名、教員約120名、保護者、一般参加などを含め、600名を超える参加者を得た。また、今回は瀬戸大橋開通30周年記念交流として、岡山県からも中学生が参加したり、カマタマーレ讃岐、香川オリーブガイナーズ、香川ファイブアローズからスポーツ選手が駆けつけて活動を共にしたりするなど、みんながつながっていじめの問題に取り組むサミットとなった。サミットの内容としては、 ・街頭アンケート(具体的な場面を用意し、このときどうするか選択肢回答式) ・パレード(子どもたちで作詞したいじめゼロの歌を披露、地域の人たちに協力を訴える) ・子ども会議(アンケートの振り返りや具体的に始めたい取り組みについて話し合う) →(例)動画を見て、被害者、加害者、観衆、傍観者の4つの立場から、「①どこに問題があったのか」「②どうしてそうなったのか」「③この後、だれとどのようにつながるか」などについて班で話し合い、それぞれの立場から、どのようにつながり合うことで、いじめの問題の解決に向かうことができるかについて考える。
□佐賀県
佐賀県HPによると、佐賀県は平成25年9月28日に施行されたいじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、平成26年9月「佐賀県いじめ防止基本方針」の策定をした。基本方針では、このように、県全体でいじめ問題に対して取り組む姿勢、学校や地域の連携が認知件数の少なさにつながっていると考えられる。
(1)学校の内外を問わず、いじめが行われないようにする。
(2)いじめは許されない行為であることを児童生徒が十分に理解できるようにする。
(3)行政、学校、地域、家庭等の連携のもと、いじめ問題を克服することを目指す。
との考え方に基づき、(1)「いじめの防止等のための組織」、(2)「いじめの防止等のための県の取組」、(3)「重大事態への対処」について定めている。
<県の取り組み・概要>
- 学校の取組への指導・支援 ・いじめの未然防止、早期発見・早期対応、再発防止など、学校の主体的・組織的な取組を積極的に指導・支援する。
- 警察との連携 ・警察が行ういじめの未然防止、早期発見・早期対応、再発防止などの取組等について連携に努める。
- 保護者・地域の取組への支援 ・社会総がかりで子どもの悩みや相談を受け止め、いじめの防止等につなげることができるよう、保護者・地域の取組を支援する
- 市町教育委員会との連携及び取組への支援等 ・市町教育委員会との積極的な連携を図り、県全体のいじめの防止等の取組のさらなる充実を図る。
- いじめの防止等のための調査研究 ・県内大学等との連携・協力のもと、いじめの防止等のための方策等に係る調査研究及び検証を実施する。
<具体的な取り組み>
・ 教職員の研修等
① いじめへの対応力の向上を図る教職員研修の推進
いじめの防止等に向けた教職員の対応力の向上を図るため、校種や経験年数に応じ、研究協議や演習等を取り入れた研修を実施する。
② いじめ問題の解決へ向けた資料等の活用
生徒指導主事研修会等において、教職員向けリーフレット「子どもたちのSOSが聞こえますか?」など、いじめの防止等に関する資料を紹介し、 これらの資料の効果的な活用を図る。
・いじめの未然防止
① 道徳教育・人権教育の改善・充実
生命を尊重する心や他者への思いやり、倫理観などの豊かな心を育み、確かな人権感覚を身に付け、望ましい人間関係を構築させるため、学校教育活動全体における位置付けを明確にした道徳教育及び人権教育の取組の改善・充実に努める。また、いじめの未然防止につながる各学校の優れた取組を紹介する。
② 児童生徒の自主的な取組への支援
児童会活動や生徒会活動などにおいて、児童生徒が自主的・自発的に いじめ問題を考え、自ら改善に向けた活動を進められるよう学校の取組を促すとともに、先進的な取組を紹介するなど、児童生徒の自主的な取組への支援を行う。また、いじめ防止子ども会議等の取組を促す。
③ インターネットを通じて行われるいじめの防止
情報モラルに関する指導者養成のための研修会を実施し、指導法の 改善・充実を図るとともに、学校における児童生徒の状況に応じた情報モラル教育の充実に努め、インターネットを通じて行われるいじめの防止を図る。
Last Update:2019/1/31
© 2018 Fumika SHIGEMOTO. All rights reserved.