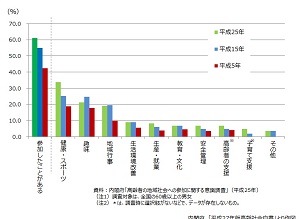西大宮への店舗誘致
−何もない土地に店舗を誘致するには−
上沼ゼミⅠ
早稲田大学社会科学部二年 上沼ゼミ 島田 怜

「お店が並んだ室内の通路のイラスト」:出所:いらすとや
章立て
- はじめに
- 西大宮の現状
- 何故これまでの西大宮への店舗誘致が少ないのか
- 事例 認知症高齢者カフェ
- 西大宮に店舗を誘致するには
- 今後の方針
1.はじめに
本研究の目的は、本稿筆者の住む西大宮の街を生活しやすくし、数年前に家を建てた家族に快適に西大宮の街で暮らしてもらうことである。
今の西大宮は住みやすいとは言えないだろう。栄高校という規模の大きな高校があり、寄り道などを避け学校の秩序を保つ必要があるとはいえ、駅の降り口にコンビニがないというのはいささか不便である。逆側の降り口にはコンビニが一軒あるのみであとは畑と住宅が広がっている。一言で表現するなら田舎のような土地である。
大型の商業施設を建てるほどのスペースはないので、衣服が買えるような中規模施設を誘致したい。また、町が発展することにより、駅の近くに病院などの医療施設も街に増えることを望んでいる。日常生活に不便をきたす程ではないが、良い状態とは言えない。今まで誰も大きなけがや病気をしていないが、この先両親がさらに年老いていけばこれらの可能性は大きくなる。できるだけ早く住みよい街にしたい。
2.西大宮の現状
2-1 西大宮の施設
西大宮には飲食店はいくつかあるものの、物を買えるような商店は少なく、マルエツという大型のスパート住宅地寄りに何軒かコンビニがあるのみである。葬儀屋のさがみ典礼と、多くの車販売店が並んでいる。駅前に腎クリニックという内科があり、駅から離れると西大宮病院という大型の病院があり、色々な診療を受けられる。住宅街の方には数件やっているかわからないいくつか歯医者がある。
埼玉栄高校とその付属の栄中学校という大きな学校があり、西大宮駅は最寄りの駅となっている。私たちの住む北口方面に栄高校の通学路があり、上記の店が並んでいる。逆口の南口には降りてすぐにコンビニが一軒あるのみでそのさきには小さな畑と住宅が並んでいる。
2-2 西大宮の交通網
国道16号線が通っており、車でのアクセスは素晴らしい。上記のお店も16号沿いに並んでおり、車での移動が一番便利である。市内循環バスが走っているため地域間の移動は容易である。2009年とに作られた西大宮駅は川越線の中でも一番新しい駅である。都心への登り電車は通勤ピーク時間で約10分に一本の間隔であり、それ以外の時間は約20分に一本の間隔で走っている。加えて、川越線しか通っていないため電車での便は悪い。
2-3 西大宮に住む人々
西大宮の属する西区の人口ピラミッドを見たところ、高齢者、3、40代とその夫婦の子供である〜9歳の子供たちが多く住んでいる。幼小学生引っ越し的安いが多いのもあってか保育園が6つほど見受けられた。小学校もあり子供を育てるには抜群の環境である。それゆえ3、40代の夫婦層が多いと考える。
小さな子供が多く育てるための施設は充実しているため、これからも新規の住民の引っ越し先として人気の候補となり得る。車までのアクセス、地域間の移動の便も良い。業種によるが、客がてんで来ないよ言うようなことはない。私が引っ越した4年間では店の退却を見たことがない。店舗が誘致されても良いような環境にも関わらすなぜ西大宮には商業施設が少ないのだろうか。
3.なぜこれまでの西大宮への店舗誘致が少ないのか
学生の多い街の治安維持のため
西大宮には幼稚園から高校まで多くの学校が建っている。中高生のたまり場になると治安の悪化や起こらなかったであろう喧嘩や騒音被害などいろいろなトラブルのきっかけとなる。
今の西大宮にはゲームセンターなどの娯楽施設はなく、学生が集まって騒いだり遊んだりできるような施設は見当たらなかった。治安の維持できそうなこの状況を変えないために店舗の誘致が行われないことが考えられる。
4.事例 認知症高齢者カフェ
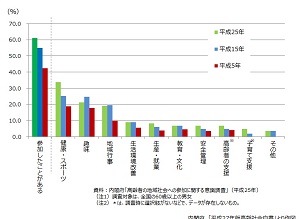
「高齢者の社会的活動」出所:健康長寿ネットより
今どきの高齢者は、活発で活動的である。趣味や地域活動に参加し、エネルギッシュに動いている。昔に比べ、年々元気になっている。医療技術の発展や健康意識の変動などもあって、人生百年時代という言葉も出てきた。
日本の千葉や大阪などの都市で、認知症高齢者の営業するカフェが存在する。これを契機に街の活性化を狙えないだろうか。「認知症の高齢者が接客する「プラチナカフェ」が10日、松戸市八ケ崎の「カフェ シャコンヌ」で開かれた。シルバーよりも輝くプラチナのように生き生きしてほしいと昨年暮れ、市の呼びかけでスタートして4回目。70代、80代のお年寄りがコーヒーや洋菓子の注文、持ち運びに表情も明るく動き回った。(2019青柳)」
この事例のように西大宮に住む活発な高齢者の力を借りられないだろうか。町の活性化伴って店舗誘致を起こす算段である。彼らにとっても地域や老人ホーム以外のコミュニティを作ることに繋がる。
しかし、このカフェの建設における費用や維持費はどこから出るのかが大きな問題となる。加えて、この認知症カフェの維持のむずかしさも新型コロナウイルスの影響で露になった。「コロナ禍で認知症の当事者や家族らが集うカフェの運営が困難になっている。いったん活動を休止したまま、再開のめどが立っていない団体も多い。感染対策をした上で再開しても、参加者が少なく、会話が弾まないケースもあるという。陸前高田市米崎町の交流施設「朝日のあたる家」は新型コロナウイルスの影響で3〜5月は休止。再開後は、感染対策としていすを同方向に並べたり、お菓子を食べないようにしたりしているが参加者数は戻っていない。施設の担当者は「外出自粛によって家に閉じこもりがちになってしまっている人もいる。(2020藤谷)」
西大宮に高齢者カフェができたとしても、一度その興味を失われてしまうと取り返すことが厳しくなる。店舗誘致を目的とするため、それ以外に目が向けられること可能性は大きい。
5.西大宮に店舗を誘致するには
検討中
今後の方針
第一に、店舗誘致が誘致される明確な基準を見出す必要がある。根拠のない誘致を目標にするわけにはいかないので、その根拠を4章の前に入れる必要がある。また、先行研究、事例が足りないので収集に時間を割くべきである。地域の特色を掴むためにもフィールドワークをさらに繰り返さなければならない。
参考文献
- いらすとや「お店が並んだ室内の通路のイラスト」URL(最終アクセス日:2021/1/29)
- ?ホームズ 「不動産売買・賃貸・住宅情報サイト」https://toushi.homes.co.jp/owner/saitama/city110101/machi.html(最終アクセス日:2021/1/29)
- 健康長寿ネット「高齢者の社会的活動」https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/tyojyu-shakai/ikigai-katsudo.html(最終アクセス日:2021/1/30)
- 青柳正悟 (2019年) 「プラチナ笑顔でおもてなし 松戸、認知症高齢者接客のカフェ /千葉県」『朝日新聞』〇年〇月〇日、pp.024?.
- 藤谷 和弘 (2020年) 「「認知症カフェ」のあり方は コロナ禍で運営困難、陸前高田で勉強会 /岩手県」『朝日新聞』〇年〇月〇日pp.019.?
Last Update:2021/01/30
©2020 REI SHIMADA. All rights reserved.